住民税は、個人住民税と法人住民税がありますが、ここでは個人住民税を扱います。
また、住民税には以下が含まれます。
(1) 都道府県が徴収する都道府県民税
(2) 市町村が徴収する市町村民税(東京23区は “特別区民税” というが、内容は同じ)

住民税の徴収方法
都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせて、市町村(東京23区は区)が徴収します。
毎年6月に、決定通知書によって納税者に税額が通知されます。
給与収入がある人の徴収方法(特別徴収)
給与収入がある人は、その人を雇用する会社に対して個人住民税が請求され、会社が給与から天引きして納付します。(”特別徴収” という)
特別徴収の納税者には、会社を経由して住民税の決定通知書が配布されます。決定通知書には、以下が記載してあります。
- 住民税の計算内容(前年1月~12月の給与収入、各種控除、年度の住民税額など)
- 住民税の徴収額(当年6月~来年5月の分割で、給与から徴収する額)
公的年金受給者のうち、一定の条件を満たす人の徴収方法(特別徴収)
公的年金(日本年金機構・企業年金基金など)の受給者のうち、以下の条件を満たす人は、年金からの天引きで住民税が徴収されます。
- 4月1日現在65歳以上、かつ前年の年金所得について個人住民税の納税義務のある人
- ただし、以下の場合を除く
- 介護保険料が年金から天引きされていない人
- 天引きされる個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える人
市区町村(東京23区は区)が住民税の決定通知書を特別徴収の対象者に送付します。
特別徴収に該当しない人の徴収方法(普通徴収)
給与・年金からの特別徴収に該当しない納税者に対しては、市区町村(東京23区は区)が納税通知書(納付書)を送付して、納税者が自分で納付します。(”普通徴収” という)
特別徴収は毎月の給与からの天引きなので年12回の徴収になるのに対して、普通徴収は一括、または4回の分割徴収になります。(6月、8月、10月、1月)
このため、普通徴収は特別徴収に較べて高額に感じるかもしれません。
住民税額の計算方法
住民税額の計算方法はややこしいですが、以下の項目で計算されます。
- 所得割
・ 前年(1/1~12/31)の所得の 10%
・ 所得(課税対象) = 年収 - 各種控除(給与所得控除、配偶者控除、社会保険料控除など) - 均等割
・年額 5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円) - 利子割
・預貯金の利子等に課税 5% - 配当割
・上場株式等の配当など、および割引債の償還差益に課税 5% - 株式等譲渡所得割
・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税 5% - 調整控除額
住民税額 =(1+2+3+4+5)ー 6 となります。
自分で計算するのは大変ですが、計算してくれるサイトがあります。リンクは控えますが、「住民税の自動計算サイト」で検索してみて下さい。
退職時の注意点
退職時に、年度の残りの住民税を一括徴収される
住民税は、6月~翌年5月の徴収予定額が決まっています。(決定通知書に記載されている)
在職中は予定に従って月々の給与から天引きされますが、退職したら天引きできなくなるため、退職月~5月分の住民税が一括で、退職月の給与から天引きされます。
5月退職の場合なら1ヵ月分のみ、6月退職の場合は1年分一括になるので、退職月によって差が大きいです。
一括徴収が厳しい場合、退職月の翌月以降の分を普通徴収に切り替える(自分で納付する)ことができます。その場合、市区町村(東京23区の場合は区)から納付の案内が来ます。普通徴収への切り替えについては、会社の給与担当者に相談してみて下さい。
退職時に次の就職先が決まっている場合は、以下のようにすると、次の就職先で月々の給与天引きにできます。
- 元の会社で、退職月の翌月以降の分を、特別徴収から普通徴収に切り替えてもらう
- 次の会社で、普通徴収から特別徴収に切り替えてもらう
次の就職先での切替えに2ヵ月かかるので、その間は普通徴収を自分で納付することになります。
退職した年は住民税がきつい
前年の収入で住民税額が決まり、6月から徴収されるので、雇用が継続していれば気になりませんが、退職して収入が減ると「収入がないのに住民税が高額」となってきついです。貯金して備えておくとよいです。

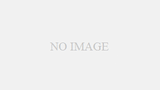
コメント