公的医療保険の種類
日本には国民皆保険制度があり、全ての国民が公的医療保険への加入を義務付けられています。
これによって、病気やケガにより病院で治療を受けたときの治療費が軽減されます。
公的医療保険は以下の種類があり、いずれかに加入することになります。
- 被用者健康保険
- 企業の従業員等であり、かつ 75歳未満の人が対象
- 対象者とその扶養者は、企業に適用されている被用者健康保険に加入する
- 被用者健康保険には、以下 ①~④ の種類がある
- ①健康保険組合がある会社に勤める人は、その健康保険組合に加入する
- 公務員、私立学校教職員、船員はそれぞれに適用される ②共済組合、または ③船員保険に加入する
- ①②③ に該当しない人は、④協会けんぽに加入する
- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上の人は、これに加入する
- 国民健康保健
- 上記 1,2 の対象外の人(自営業者など)は、以下 ④⑤ のいずれかに加入する
(どちらも国民健康保険法に基づいて運営されている)- ④ 居住する市区町村で運営されている国民健康保険
- 市区町村によって保険料が異なる
- ⑤ 国民健康保険組合(同業同種の個人事業の自営業者で組織する組合)の国民健康保険
- 医師、歯科医師、薬剤師、建設、税理士、弁護士など多くの組合がある
- 組合によって保険料が異なる
- ④ 居住する市区町村で運営されている国民健康保険
- 上記 1,2 の対象外の人(自営業者など)は、以下 ④⑤ のいずれかに加入する
退職すると被用者保険から脱退して、別の公的医療保険に加入する
退職した人は、それまで加入していた被用者保険から脱退することになります。
そして速やかに別の公的医療保険に加入しなければなりません。
“別の公的医療保険” については、75歳になるまでは下記 1~3 の選択肢があります。
75歳になると例外なく、後期高齢者医療制度に加入することになります。
- 被用者保険の任意継続
- 在職中に加入していた被用者保険を、退職後2年間を限度に延長することができる
・ 保険料は在職中より高くなる
(在職中は保険料を会社と本人が折半で負担、任意継続では全額本人負担)
・ 任意継続の保険料は、組合等に問い合せないと分からない
(保険料の決定方法は組合等によって異なり、本人の在職中の収入等も関係する) - (在職中に加入していた被用者保険と同様に)扶養の扱いがある
- 2021年までは任意継続に加入すると2年縛りで中途脱退できないことになっていた(実は脱退する方法はあった)が、2022年1月から正式に中途脱退できるようになった
- 在職中に加入していた被用者保険を、退職後2年間を限度に延長することができる
- 国民健康保険
- 国民健康保険は市区町村で運営されていて、保険料は市区町村によって異なる
- 国民健康保険には扶養の扱いがない
- 家族の複数名が国民健康保険に加入する場合、一人ひとりに保険料がかかる
- 保険料の納付義務は世帯主にある(家族の保険料を合算して、世帯主が納付)
- 会社勤めしている家族の扶養に入る
- 生計を一にする家族(配偶者・子)が会社勤めしている場合、
その家族の扶養に入ることで、その家族の被用者保険に加入できる - その家族の被用者保険料は増額されないので、とてもお得
- ただし、扶養に入れる条件は厳しい(組合等によって条件が異なる)
- 生計を一にする家族(配偶者・子)が会社勤めしている場合、
被用者保険/任意継続から国民健康保険に切り替える場合、被用者保険/任意継続で扶養の扱いになっていた家族一人ひとりについて、国民健康保険の保険料がかかります。
上記 1~3 の他に、一部の健康保険組合には “特例退職被保険者制度” というものがあり、退職後から 75歳になるまで被用者保険を延長できます。利用できる人は限られますが、医療費の自己負担が小さいとか、扶養の扱いがあるというメリットがあります。
退職したら、どの公的医療保険を選択したらよいか?
前項の 1~3 のどれを選択したらよいでしょうか。
保険料に注目すると、
- 3. は保険料が無料なので加入できればお得です。でも、加入条件(年収)が厳しいです。
- 1. と 2. を比較すると、組合等によりますが多くの場合、退職時は 1. が安いと思います。
- 2. は、前年の所得で保険料が決まるので、退職時は高く、1年後は安くなるケースが多いと思います。
保険料の他に、1~3 で利用できるサービスが異なるということもあるので、それも考慮して選んで下さい。(任意継続の場合、組合が運営する診療所や人間ドックを利用できる等)
おそらく、退職時に任意継続を選択して、1年後に国民健康保険に切り替えるというパターンが多いかと思います。
任意継続の保険料は、組合等に問い合わせて下さい。
国民健康保険の保険料を計算してくれるサイトがあります。リンクは控えますが、「国民健康保険の自動計算サイト」で検索してみて下さい。
保険料の納付方法
在職中の保険料は給与から天引きされていましたが、退職後は、任意継続と国民健康保険で、納付方法が異なります。
任意継続の場合
月払いと一括払いがあります。納付先は被用健康保険を運営する組合等になります。
- 月払い(口座振替)
- 初回分保険料を振込など指定の方法で納付 → 納付後に新しい保険証が発行される
・ 初回分保険料は、組合によって1ヵ月分だったり、3ヵ月分だったりする
- 「3ヵ月」の理由は、口座振替の手続きが完了するまでの期間を見込んでいるから
- 「1ヵ月」の場合も、続く2ヵ月間は振込になる
・ 3ヵ月分一括だと 10万円とか結構高額になる - 初回分以降は、口座振替
- 口座振替について
- 振替手数料がかかる
- 振替日は組合等によって異なる
- 口座の残高不足で振替できなかった場合、任意継続が強制脱退になる
→ そうなった場合は、国民健康保険に切り替えなければならない
- 初回分保険料を振込など指定の方法で納付 → 納付後に新しい保険証が発行される
- 一括払い(振込)
- 1年分の一括払い、半年分の一括払いがある
- 保険料の割引がある
国民健康保険の場合
特別徴収と普通徴収があります。納付先は国民健康保険を運営する市区町村になります。
- 特別徴収
以下の条件を全て満たす場合、世帯主の公的年金から保険料を天引きする(年金に合わせて、年6回)- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯内で国民健康保険に加入している人が全員、65歳以上75歳未満であること
- 一定の年金収入があること
- 特別徴収の対象となる一年間の年金額が18万円以上、かつ、
国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと
- 特別徴収の対象となる一年間の年金額が18万円以上、かつ、
- 普通徴収
- 特別徴収に該当しない場合、世帯主が納付書や口座振替などで納付する
- 納付の月と回数は、市区町村によって異なる
- 年度の保険料を、6月~3月の毎月10回で納付、とか
- 〃 7月~2月の毎月8回で納付、など

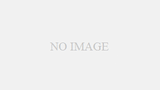
コメント